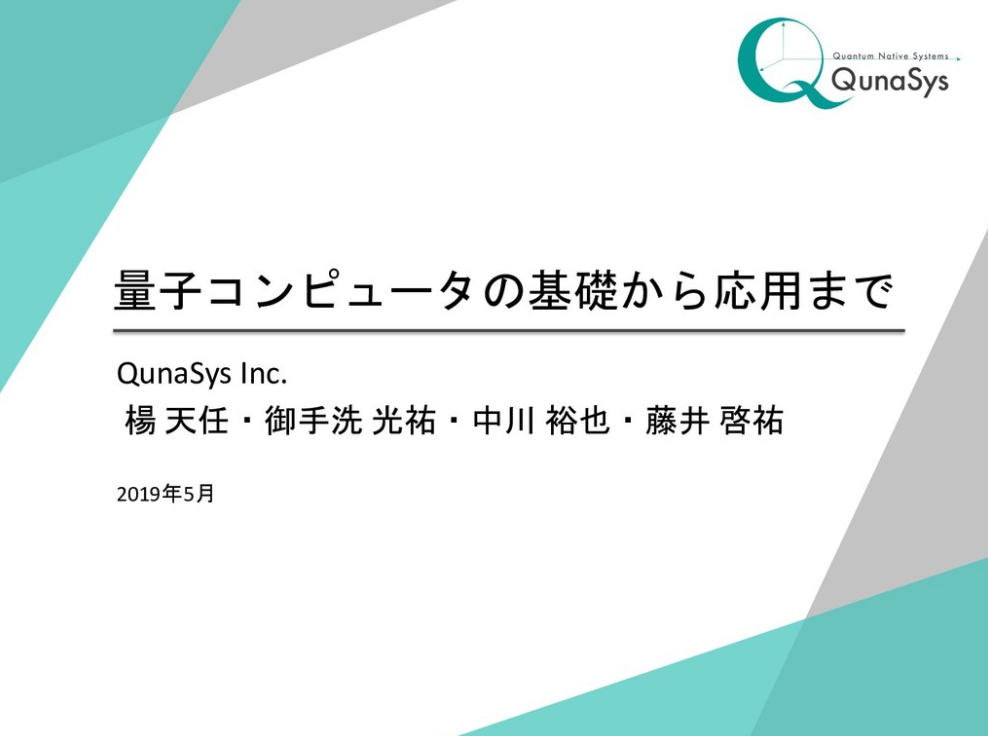第0章 そもそも量子コンピュータとは?¶
量子コンピュータというアイディア¶
量子コンピュータのアイディア自体は古く、エッセイ「ご冗談でしょう、ファインマンさん」でも有名な物理学者リチャード・ファインマンが、1982年に「自然をシミュレーションしたければ、量子力学の原理でコンピュータを作らなくてはならない」と述べたことに端を発する[1]。そして、1985年にオックスフォード大学の物理学者デイビット・ドイチュによって量子コンピュータが理論的に定式化された[2]。
量子コンピュータと従来の古典コンピュータの最も異なる点は、その情報の表し方である。古典コンピュータの内部では、情報は0か1、どちらか1つの状態を取ることのできる「古典ビット」で表現される。これに対し、量子コンピュータの内部では、情報は0と1の両方の状態を同時に取ることのできる「量子ビット」で表現される(詳細はこれからQuantum Native Dojoで学んでいくのでご安心を)。量子コンピュータは、量子ビットを用いて多数の計算を同時に行い、その結果をうまく処理することで、古典コンピュータと比べて飛躍的に高速に計算を行える場合がある。
どのように役に立つのか¶
さきほど場合があると強調したのは、現実にある全ての問題(タスク)を、量子コンピュータが高速に計算できるわけではないからだ。むしろ、量子コンピュータの方が古典コンピュータより高速なのかどうか未だに分かっていない問題の方が圧倒的に多い。それでも、一部の問題については量子コンピュータの方が現状の古典コンピュータのアルゴリズムよりも高速であることが証明されている。その代表例が素因数分解である。
素因数分解は、\(30 = 2\times3\times5\) などの簡単な場合なら暗算でも計算できるが、分解すべき整数の桁数が大きくなってくると、最高レベルの速度を持つスーパーコンピュータでさえ、その計算には年単位・あるいは宇宙の寿命ほどの時間が必要になる。この「解くのに時間がかかる」ことを利用したのが、現在の暗号通信・情報セキュリティに広く用いられているRSA暗号である。しかし、1995年に米国の数学者ピーター・ショアが、古典よりも圧倒的に速く素因数分解を行う量子アルゴリズムを見つけた[3]ことで、一気に量子コンピュータに注目が集まることになった。
素因数分解の他にも、量子コンピュータの方が現状の古典コンピュータよりも高速であると証明されている問題がいくつかある。例えば、整理されていないデータから目的のデータを探し出す探索問題 (8-2. グローバーのアルゴリズム)や、連立一次方程式の解を求める問題 (7-2. Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL) アルゴリズム) などである。これらの問題は、流体解析・電磁気解析・機械学習など、現代社会を支える様々な科学技術計算に活用できる。さらに、万物は元をたどれば量子力学に従っているため、ファインマンやドイチュが考えたように、究極の自然現象シミュレーターとして量子コンピュータを活用し、物質設計や素材開発を行うことも考案されている (第6章 量子化学計算)。
このように、量子コンピュータによって世の中の全ての計算が高速化される訳でないものの、現代社会に与えるインパクトは計り知れないものがある。
量子誤り訂正¶
ここまで述べたのは、量子コンピュータの理論的な話である。理論的に速く計算できると証明できても、応用するには実際に計算を行うハードウェアが必要になる。量子コンピュータのハードウェアを製作する研究は世界中で広く行われているが、課題はまだまだ多いのが現状である。もっとも大きな課題の一つが、ノイズである。量子ビットは古典ビットと比べて磁場や温度揺らぎなどの外部ノイズを非常に受けやすく、保持していた情報をすぐに失ってしまう。2019年現在でも、数個〜数十個程度の量子ビットを連結し、より安定に長く動作させる方法を探っているような段階である。
そのようなノイズの問題を克服するために研究されているのが、量子誤り訂正の技術である (第9章 量子誤り訂正)。量子誤り訂正は、計算途中に生じた量子ビットの誤り(エラー)を検知し、本来の状態に訂正する技術で、理論的には様々な手法が提案されている(なお、我々が普段使っている古典コンピュータにも古典ビットの誤り訂正機能が搭載されている。この機能のおかけで、我々はPC内のデータが突然無くなることを気にせずに暮らせるのである)。しかし、量子誤り訂正は単なる量子ビットの作製・動作実現よりもはるかに技術的難易度が高く、誤り訂正機能を持った量子ビットを集積化可能な形で作るには少なくともあと10年は必要であると言われている。
そして、前項であげた量子コンピュータの様々な応用を実用的な規模で実行するには、誤り訂正機能を持った量子ビットが1000個単位で必要となることから、真の量子コンピュータの現実的応用は数十年先になると考えられている。
NISQ (Noisy Intermidiate-Scale Quantum) デバイスの時代¶
では我々が量子コンピュータの恩恵を受けるには、あと何十年も待たないといけないのだろうか。「そんなことで手をこまねいているわけにはいかない!」ということで、科学者たちは様々な方法で量子コンピュータの有用性を示そうと模索している。その中で現在最も注目されており、世界中で研究が進められているのがNoisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) デバイスという量子コンピュータである。
NISQデバイスの定義は「ノイズを含む(誤り訂正機能を持たない)、中規模(〜数百qubit)な量子デバイス」であり、これであれば数年以内の実用化が可能であると考えられている。NISQデバイスは、誤り訂正機能がないので限られた量子アルゴリズムしか実行できないものの、量子化学計算や機械学習といった領域で、現在の古典コンピュータを凌駕する性能を発揮すると予想されている(第4章・第5章・第6章参照)。
NISQデバイスまで含めれば、量子コンピュータが応用され始めるのはそう遠くない未来なのである。このQuantum Native Dojoを通して、そうした量子コンピュータ応用の最先端に触れるための知識を皆様に身につけていただければ幸いである。
参考文献¶
Feynman, “Simulating physics with computers”, International Journal of Theoretical Physics 21, 467 (pdfリンク)
Deutsch, “Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer” Proceedings of the Royal Society of London A 400, 97 (1985) (pdfリンク)
Shor, “Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer”, IAM J.Sci.Statist.Comput. 26 (1997) 1484 (pdfリンク)
量子コンピュータの基礎から応用までに関するスライド¶
量子コンピュータの動作原理や応用アプリケーション、政府・企業の動きに関したさらに詳しい解説は、 Quantum Summit 2019の講演をまとめたスライドをご覧ください。
コラム:量子ビット・量子ゲート操作を物理的にどう実現するか¶
実際の量子コンピュータを構成する量子ビットはいったいどのように作られ、量子ゲート操作はどのように実行されているのだろうか。
量子ビットを実現する方法は1995年頃から複数の有望な方式(物理系)が提案されており、超伝導回路方式・イオントラップ方式・光方式などがある。各方式によって、現在実現できている量子ビット数や量子ビットの寿命(コヒーレンス時間)、エラー率等に違いがあり、世界各国で研究が盛んに進められている。
数々の量子ビット実現方式の中で、最も広く知られている方式は超伝導回路を用いた超伝導量子ビットである。これは1999年に当時NECに所属していた中村泰信(現東京大学教授)・蔡兆申(現東京理科大学教授)らによって世界で初めて製作された量子ビットで、超伝導物質を用いたジョセフソン接合と呼ばれる微細な構造を作ることで量子ビットを実現している。量子ゲート操作は、マイクロ波(電磁波の一種)のパルスをターゲットの量子ビットに送ることで実現される。また、量子ビットの測定は測定用の超伝導回路を量子ビットにつけることで行われる。
超伝導回路方式は、GoogleやRigetti conmputingが数十量子ビットの素子の開発を発表するなど、2019年3月現在で最も有望な量子コンピュータ実現方式であると言える。
量子ビットの実現方法について、より深く知りたい場合には以下を参考にされたい:
Qmedia 量子コンピュータを実現するハードウェア
レビュー論文:T. D. Ladd et al. , “Quantum Computing”, Nature, 464, 45 (2010). https://arxiv.org/abs/1009.2267
Nielsen-Chuang 第7章
Quantum computers: physical realization